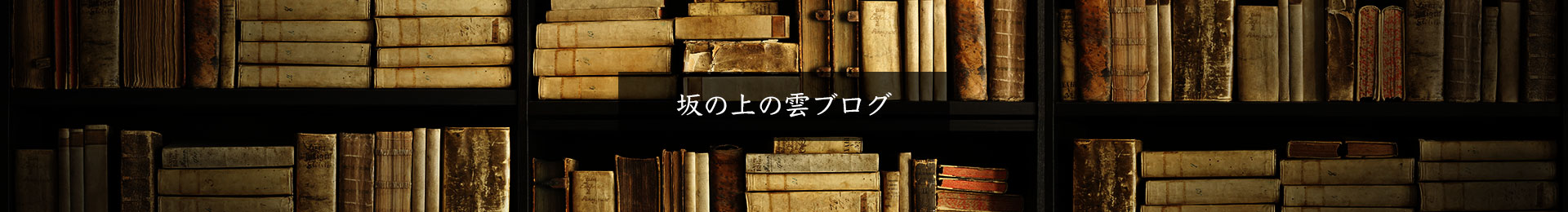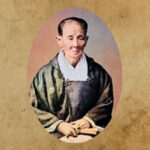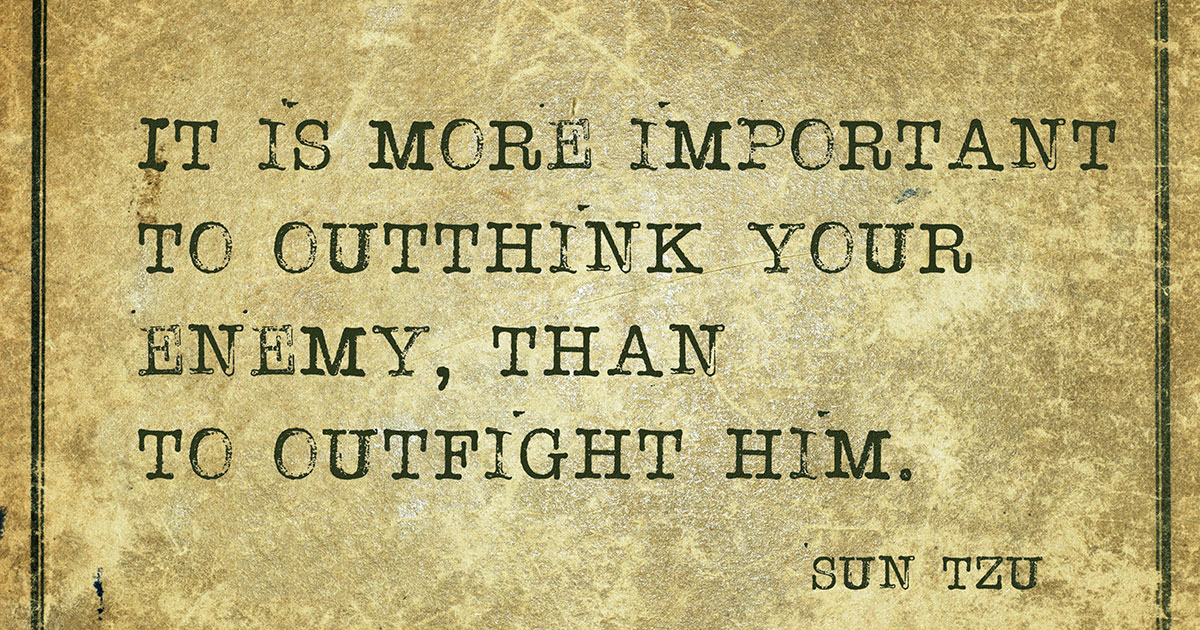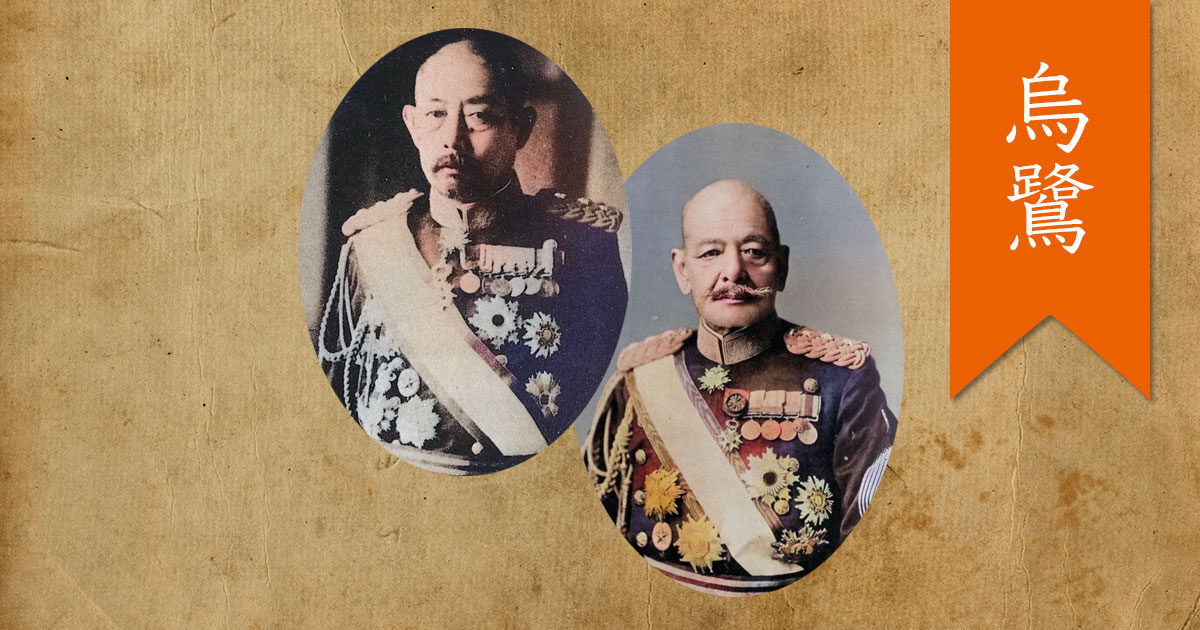正岡子規の母、正岡八重

正岡八重

1845年(弘化2年)、伊予松山藩の藩校「明教館」の教授で漢学者の大原観山の長女として生まれる。
33歳の時に、御馬廻加番であった正岡常尚の後妻に入った。 常尚の先妻は、長男を生むとすぐに亡くなり、その長男も天折していた。
正岡家は常尚まで、8代200年間松山藩に仕えた武家である。しかし幕府が崩壊し、明治の新しい時代の波に乗れなかった常尚は鬱々とした日を酒で紛らわし、その結果、酒に命を取られることになる。
八重は、もともと口数の少ない物静かな女性であったが、後家になって変わる。 特に片親ゆえと言われないように、子供たちの躾には厳しくなった。 また、正岡家が家事で焼けた時も、嫁入り道具何一つ残らないで焼けたのに、それすら残念そうな顔一つしなかったと話草になったほでで、何事にも驚かない、泰然自若とした女性であったと云う。
1927年(昭和2年)没
子規の想い出
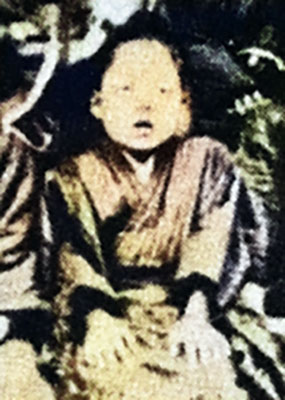
赤ン坊の時はそりゃ丸い顔てて、丸い顔てて、よっぽど見苦しい顔でございました。鼻が低い低い妙な顔で、ようまア此頃のように高くなったものじゃと思います。十八位からようよう人並の顔になったので、ほんとに見苦しうございました。大人になってあれ程顔の変った者もありますまい。
六つ位からもう髷を結いました。父親が早くなくたったので殿様へお目見えをせんならんので(大抵八つ位からお目見えする)ございましたが、御維新になってそれはせずにすみました。髷を結うたなり、三並(良民)のと二人で小学校(法龍寺内)へ通いましたが、たった二人ぎりが髷を結うて居るので、大変いやがりまして、切って呉れ呉れ言いました。
中学に行きよります中に、東京へ出たがって出たがってやかましういうて居りましたが、加藤の弟(恒忠)から、西洋へ行く前に来いというて来ましたので、飛上って喜んで、丁度大原の叔父は留守でございましたから、佐伯の叔父の処へ飛んで往って・・・来いという手紙の来た翌々日松山を出立しました。単衣物を一枚こしらへるというので、夜通し縫うた事など覚えて居ります。
『子規言行録』より